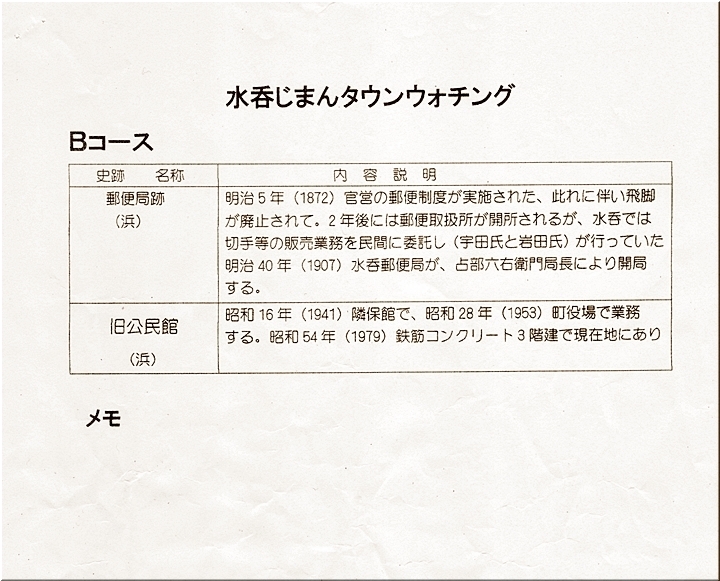
| 2024/11/03(日) 水呑学区「ふれあい文化祭〝史跡巡り〟」 <3/5> |
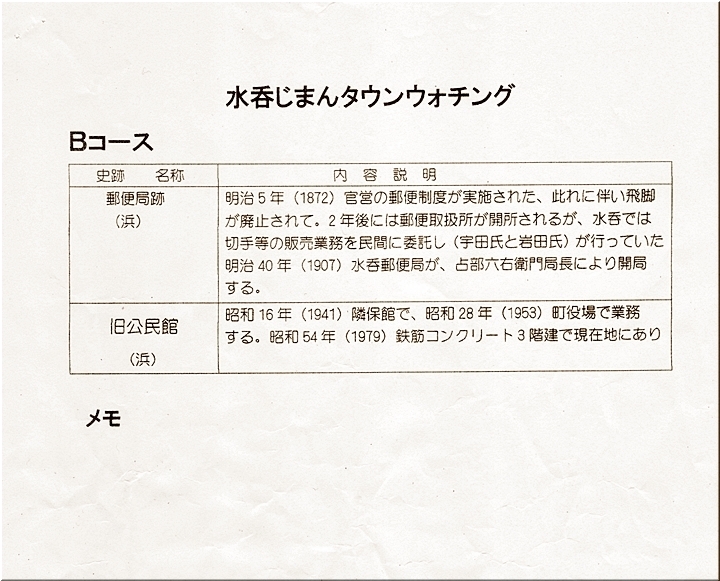

定刻が近付いて来ましたけど、〝史跡めぐり〟出発前に、まずは全員で集合写真を…ザッと眼で数えてみますと、お世話して頂く方を含め30名近くの皆様です。
そして、定刻に〝水呑交流館〟をスタートとなりました。
まず、最初に向かいますのは、お寺への参道入口に存在します、〝大法界碑〟と〝「高札場・札場」跡〟です。大法界に隣接の建物が〝札場〟跡ですネ。
◆大法界
法界とは仏の世界を意味し、亡くなられた方の供養や、自然災害や疫病に苦しむ人々のご加護を求めたり、お寺の参道脇にはこれより聖域に入る結界を示す等、色々あります。
天保元年(1830)の洪水による飢餓で騒動が起こり、この責めを負って庄屋小林嘉忠治が処刑された。その徳を慕って1833年建てられたものです。
◆高札場・札場
江戸時代に福山藩の高札場木の板に法令を書き、門前や路頭、辻などに掲げた場所(藩が庶民を統治する上での根本法を掲げる板)で、ここがその場所。竹内邸の屋号は現在でも札場(ふだば)という。

法界碑脇には、〝水呑歴史資料保存会〟による説明板が…これには、こんな記載がありました(^.-)☆
◆高札場「札場」跡
木の板に法令を書き、門前や路頭、辻などに掲げた場所。
古代より類似したものがあり、近世には町や村に高札を掲げる高札場が設けられた。高札には、公儀(幕府)高札と藩高札があり、広い意味での治安や秩序の維持に関するものが多く、法令の周知徹底というより、幕府権力の威光を象徴するものとして機能した。
◆大法界
「水呑千軒みな法華」と言われたように、水呑には妙性山妙顕寺をはじめ数多くの寺院があり、「南無妙法蓮華経」の髭題目を刻んだ法界碑が至る所にあります。法界とは「仏の世界」を意味し、法界碑は亡くなられた方の供養や、自然災害や疫病に苦しむ人々の加護を求めたり、寺の参道脇にはこれより聖域に入る結界を示す等、様々な目的を持って建てられています。
この大法界は、正面に「南無妙法蓮華経日蓮大菩薩」、向かって右側に「天保四癸巳年三月吉良辰」、台座に「村講中」と刻印されています。
巨大な自然石を組み合わせ、高さは5.3mあります。古老の話によると、対岸の箕島から船で運ばれて来たと言われ、福山でも最大級の大きさを誇り、水呑信者の信仰心の深さがうかがえます。
参考文献『福山再発見 -- 知って欲しい文化財』『歴史学事典9法と秩序』『福山市史』
水呑学区まちづくり推進委員会 水呑歴史民俗資料保存会 平成30年3月設置
大法界碑からは、参道を、〝水呑啓蒙所跡〟〝仁王門〟へと向かいます。
◆水呑啓蒙所
明治5年(1782)に初等教育機関として設置、1873年対蓑(たいさい)小学校と改称、明治9年(1876)水呑小学校に改められた。明治41年(1908)に現在地に移転新築された。
◆水呑啓蒙所跡
水呑に於いて、此処は啓蒙所と小学校の跡地であります。
水呑村では明治5年(1872)3月にここ(土居)に水呑村啓蒙所が建立されました。又、同6年対蓑(たいさい)小学校と改称、同9年水呑小学校となる。
此処は別名学校屋敷とも言います。当時の校内は、東西二十一間(約42m)、南北十一間(約22m)でした。
明治38年(1905)には敷地八百坪、校舎三十一坪と拡張されていました。此処には明治41年(1908)頃まで小学校がありました。当時の生徒数は225人いました。この小学校の廃材は各郷の集会所に再利用されたそうです。(参考資料--水呑町史、水呑のあゆみ)
・鬼瓦 -- 当時の屋根瓦は現在の鍛冶屋集会所に使われています。
水呑学区まちづくり推進委員会 水呑歴史民俗資料保存会 平成27年11月設置
◆仁王門
現在の仁王門は参道にあるが、初代は本堂の前に寛永6年(1629)建立され、寛文10年(1670)に再建され、明治12年(1879)現在地に移転、仁王像は天保8年(1837)に再建されています。仁王像は阿形(右・あぎょう)、吽形(左・うんぎょう)がある。
仁王門をくぐり石段を上がると、右に〝玉泉寺〟、左に〝壽泉寺〟そのまた左に〝玄祥寺〟が存在です。
・玉泉寺 -- 寛永2年(1625)の創建、開基妙顕寺18世日意上人。
・壽泉寺 -- 正保4年(1647)の創建、開基妙顕寺18世日意上人。
・玄祥寺 -- 元和7年(1621)の創建、開基妙顕寺18世日意上人。

三ヶ寺が並びの場所からまた石段を上がりますと、妙顕寺境内へと到着です。
ここには、本堂の前に、日像菩薩と妙性上人・本性上人の銅像が存在です。
◆妙顕寺
日蓮宗の寺院で京都妙顕寺の末寺、中本寺の資格であった
水呑村鍛冶屋に住居していた妙性・本性兄弟は、教化に浴し得度して、妙性ヶ滝の傍らに庵室を結び、日像菩薩の弟子で大覚え大僧正妙実上人が、延文元年(1356)、これを妙性山妙顕寺と名付けた。
西龍華 妙性山 妙顕寺
-- 水呑町史より --
◆妙顕寺 銅像〝日像菩薩と妙性上人・本性上人〟
妙顕寺開山650年記念事業として、西龍華妙性山妙顕寺由緒三体尊像、龍華樹院日像菩薩の座下に宿として教導を受けた刀匠法華一乗兄弟妙性(右)本性(左)三体尊像として建立。
2006年4月8日正吉也、妙顕寺檀信徒一同
そぅそぅ、イィ機会ですから、今回の史跡巡りの講師を務められました根師sanに、鐘楼付近の土塀の隅っこに置かれています二体の象について「これは、何?」と尋ねますと、誰が、いつ、何の為に置いたのか分からない…との事でありました。
お寺さんが置かれた訳でもないようですから、檀信徒のどなたかが設置されましたのでしょうねぇ~
妙顕寺でのお話しが終わりますと、次は〝妙性ヶ滝〟方向へと向かいます(^-^)//"
| ← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |